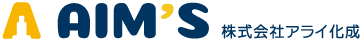目次
近年、地球環境問題への関心が高まる中で、「サステナブル素材」への注目はますます強まっています。
特に、私たちの生活に深く根付いているプラスチックについては、その利便性の一方で、海洋汚染や資源枯渇といった課題が深刻化しています。
こうした背景から、従来の石油由来プラスチックに代わる、環境に配慮したサステナブルなプラスチックの導入が企業にとって重要な経営課題となりつつあります。
この記事では、企業の製品開発や企画担当者の皆様が知りたいサステナブルなプラスチックの種類や特徴、メリット・デメリット、そして自社に最適な素材を選ぶためのポイントを、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説します。
サステナブルなプラスチックが注目される背景

なぜ今、これほどまでにサステナブルなプラスチックが求められているのでしょうか。
その背景には、複合的な要因が存在します。
世界的なプラスチック問題の深刻化
私たちの生活を豊かにしてきたプラスチックですが、その廃棄物が環境に与える影響は計り知れません。
特に、適切に処理されずに海へ流出したプラスチックごみは、海洋生物の生態系を脅かす「海洋プラスチック問題」として世界的な課題となっています。直径5mm以下のマイクロプラスチックとなり、食物連鎖を通じて人体への影響も懸念されています。
このような問題意識の高まりが、使い捨てプラスチックからの脱却と、環境負荷の少ない代替素材への転換を加速させているのです。
企業の環境責任(SDGs・ESG投資)への関心の高まり
現代の企業経営において、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視する「ESG投資」の流れが世界的に拡大しています。
投資家は、企業の財務情報だけでなく、サステナビリティへの取り組みを重要な判断基準と見なすようになりました。
また、持続可能な開発目標(SDGs)への貢献も、企業の社会的責任として強く求められています。サステナブルなプラスチックを導入することは、これらの要請に応え、企業価値を向上させるための具体的なアクションの一つとして位置づけられています。
国の政策と法規制の動向
世界各国でプラスチックごみ削減に向けた法規制が強化されています。日本でも2022年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環法)」が施行されました。
この法律は、製品の設計から廃棄物処理に至るまでのライフサイクル全体で、プラスチックの資源循環(3R+Renewable)を促進することを目的としています。
具体的には、特定プラスチック使用製品の使用合理化や、排出事業者の再資源化努力などが求められており、企業はこれまで以上に環境配慮設計への転換を迫られています。
| 政策・法律 | 施行年 | 主な目的 |
| プラスチック資源循環促進法 | 2022年 | 製品設計から廃棄までプラスチックの資源循環を促進 |
| レジ袋有料化義務化 | 2020年 | 消費者のライフスタイル変革を促し、 プラスチックごみ削減への意識を高める |
| 資源有効利用促進法 | 2001年 | 3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進し、循環型社会の形成を目指す |
参考:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 | e-Gov 法令検索、cms_local204_200430_12-3.pdf、3R政策(METI/経済産業省)
サステナブルなプラスチック「バイオプラスチック」とは?
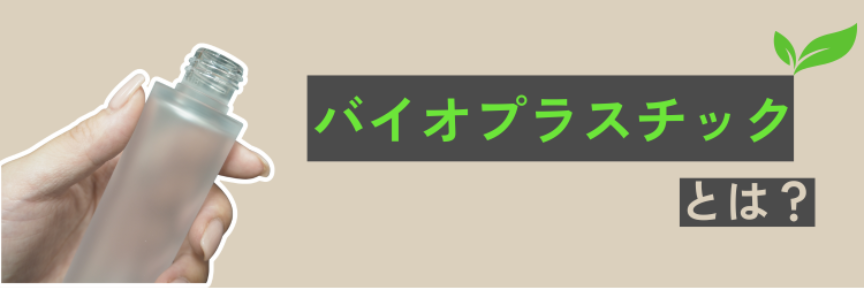
環境に配慮したプラスチックとして注目される「バイオプラスチック」。しかし、その定義は一つではありません。
ここでは、その全体像を正しく理解するための基本的な分類について解説します。
バイオプラスチックの全体像を理解する
バイオプラスチックは、「バイオマスプラスチック」と「生分解性プラスチック」という2つの異なる性質を持つプラスチックの総称です。
重要なのは、「バイオマスプラスチックであり、かつ生分解性を持つもの」「バイオマスプラスチックだが、生分解性は持たないもの」「石油由来だが、生分解性を持つもの」の3つのタイプが存在する点です。
この違いを理解することが、素材選定の第一歩となります。
「バイオマスプラスチック」の定義と特徴
バイオマスプラスチックは、トウモロコシやサトウキビといった植物などの再生可能な生物資源(バイオマス)を原料にして作られるプラスチックです。
最大の特徴は、原料となる植物が成長過程で光合成によりCO2を吸収するため、燃焼時にCO2を排出しても大気中のCO2総量を増やさない「カーボンニュートラル」という性質を持つ点です。
これにより、地球温暖化の抑制に貢献できます。ただし、必ずしも生分解性を持つわけではないため、リサイクルプロセスは従来のプラスチックと同様に考える必要があります。
「生分解性プラスチック」の定義と特徴
生分解性プラスチックは、使用後に土中や水中の微生物の働きによって、最終的に水と二酸化炭素に分解される性質を持つプラスチックです。
この性質により、万が一自然界に流出してしまった場合でも、環境中に長期間残留するリスクを低減できます。
原料は、バイオマス由来のものと、石油由来のものがあります。
注意点として、分解には特定の温度や湿度、微生物の存在が必要であり、あらゆる環境で速やかに分解されるわけではないという点が挙げられます。
主要なバイオマスプラスチックの種類と特徴

バイオマスプラスチックには様々な種類があり、それぞれ特性や用途が異なります。ここでは代表的なものを紹介します。
バイオPE(バイオポリエチレン)
サトウキビの搾りかすから作られるバイオエタノールを原料としています。
従来の石油由来ポリエチレン(PE)と全く同じ化学構造を持つため、物性も同等で、既存の成形機やリサイクル設備をそのまま利用できるのが大きな利点です。
シャンプーのボトルや食品包装フィルムなど、幅広い製品に使用されています。
バイオPET(バイオポリエチレンテレフタレート)
バイオPETは、原料の一部(モノエチレングリコール)にサトウキビ由来のバイオマス資源を使用しています。
石油由来のPETと同様に、透明性や強度に優れており、リサイクルも可能です。飲料用のペットボトルや繊維製品などに利用されています。
PLA(ポリ乳酸)
トウモロコシやジャガイモのでんぷんを乳酸発酵させて作られる、バイオマスプラスチックであり、かつ生分解性も持つ代表的な素材です。
透明性が高く硬いのが特徴ですが、耐熱性や耐衝撃性は他のプラスチックに劣るという課題もあります。食品トレイや3Dプリンターのフィラメント、農業用フィルムなどに使用されています。
その他のバイオマスプラスチック
その他にも、ひまし油を原料とする「バイオPA(ポリアミド)」や、木材パルプを主原料とする「パルプラス」など、様々な特徴を持つバイオマスプラスチックが開発されています。
| 種類 | 原料 | 特徴 | 主な用途 |
| バイオPE | サトウキビ | 石油由来PEと物性が同等、リサイクル容易 | ボトル、食品包装フィルム |
| バイオPET | サトウキビ、 石油 | 石油由来PETと物性が同等、透明性・強度良好 | 飲料ボトル、 繊維製品 |
| PLA | トウモロコシ、サトウキビ、 ジャガイモ | 透明性、硬質、生分解性を持つ | 食品トレイ、3Dプリンター材料 |
| バイオPA | ひまし油 | 耐熱性、柔軟性に優れる | 自動車部品、 スポーツ用品 |
主要な生分解性プラスチックの種類と特徴

次に、微生物によって分解される性質を持つ生分解性プラスチックの代表例を見ていきましょう。
PLA(ポリ乳酸)※バイオマス由来
前述の通り、PLAはバイオマスプラスチックでありながら、コンポスト(堆肥化)などの特定の条件下で微生物によって分解される生分解性を持ち合わせています。
このデュアルな特性から、多くの製品で採用が進んでいます。
PHA(ポリヒドロキシアルカノエート)※バイオマス由来
植物油などを微生物に食べさせて、その体内に蓄積されたポリマーを抽出して作られるプラスチックです。
PHAの大きな特徴は、土中だけでなく海洋中でも生分解されやすい点にあり、海洋プラスチックごみ問題への貢献が特に期待されています。
PBAT(ポリブチレンアジペートテレフタレート)※石油由来
PBATは、石油を原料としながらも、生分解性を持つプラスチックです。
柔軟性が高く加工しやすいという特徴があり、PLAと混合してフィルムの柔軟性を高めるなどの目的で使用されることもあります。
農業用のマルチフィルムやコンポスト可能なごみ袋などに利用されています。
| 種類 | 原料 | 特徴 | 分解環境 |
| PLA | バイオマス | 硬質で透明性が高い | コンポスト、土壌 |
| PHA | バイオマス | 海水中でも生分解されやすい | 海水、土壌、コンポスト |
| PBAT | 石油 | 柔軟性が高く加工しやすい | コンポスト、土壌 |
サステナブルなプラスチックを導入するメリット

企業がサステナブルなプラスチックを導入することで、環境面だけでなく、ビジネス面においても多くのメリットが期待できます。
環境負荷の低減に貢献する
バイオマスプラスチックの利用は、化石資源の使用量を削減し、カーボンニュートラルの観点から温室効果ガスの排出抑制に繋がります。
また、生分解性プラスチックは、適正に処理することでプラスチックごみ問題、特に海洋プラスチック問題の緩和に貢献する可能性があります。
企業のブランドイメージを向上させる
環境問題への取り組みを積極的にアピールすることは、企業の社会的責任(CSR)を果たしている証となり、消費者や取引先からの信頼を高めます。
サステナブルな素材を使用した製品は、環境意識の高い消費者にとって魅力的に映り、企業のブランドイメージ向上に直結します。
新たな顧客層へアピールできる
環境配慮を製品選択の重要な基準とする消費者は年々増加しています。
これまでアプローチできなかった新たな顧客層に対して、サステナブルな製品を通じて訴求することが可能になります。
これは、市場における競争優位性を確立し、新たなビジネスチャンスを創出するきっかけとなり得ます。
| メリット | 具体的な内容 | 関連する経営課題 |
| 環境負荷の低減 | 温室効果ガス排出抑制、プラスチックごみ問題への貢献 | 脱炭素経営、サーキュラーエコノミーへの移行 |
| ブランドイメージ向上 | CSR活動のアピール、消費者や取引先からの信頼獲得 | 企業価値向上、ステークホルダーエンゲージメント |
| 新たな顧客層への訴求 | 環境意識の高い消費者へのアピール、市場での競争優位性確保 | 新規市場開拓、売上拡大 |
サステナブルなプラスチックを導入するデメリットと課題

多くのメリットがある一方で、サステナブルなプラスチックの導入にはいくつかの課題も存在します。これらを事前に把握し、対策を検討することが重要です。
コストが割高になる可能性がある
現状では、多くのサステナブルなプラスチックは、従来の石油由来プラスチックと比較して製造コストが高い傾向にあります。
特に、原料の調達や新しい製造プロセスが価格に反映されるため、製品の最終価格に影響を与える可能性があります。
ただし、技術開発や量産化によって、将来的にはコスト差が縮小していくことが期待されます。
素材によっては性能(耐熱性・耐衝撃性)に制約がある
例えば、代表的な素材であるPLAは、硬質である一方で、耐熱性や耐衝撃性が低いという弱点があります。
そのため、高温になる製品や強い衝撃が加わる可能性のある製品への使用には注意が必要です。
用途に応じて、他の素材と混合するなどの改良や、適した素材を選択する必要があります。
リサイクルや廃棄のインフラが未整備である
サステナブルなプラスチックがその環境性能を最大限に発揮するためには、適切な分別収集、リサイクル、コンポスト化の社会システムが不可欠です。
しかし、現状ではこれらのインフラが十分に整備されているとは言えず、せっかくの素材が適切に処理されないケースも少なくありません。
消費者への正しい廃棄方法の周知も今後の課題です。
| デメリット・課題 | 具体的な内容 | 検討すべき対策 |
| コスト | 従来のプラスチックより製造コストが高い傾向にある | 補助金・助成金の活用、製品の付加価値として価格設定を検討 |
| 性能面の制約 | 素材により耐熱性や耐衝撃性が劣る場合がある | 製品の要求性能に合った素材の選定、複合材料化の検討 |
| インフラの未整備 | 分別・回収・リサイクル・コンポスト化の社会システムが不十分 | 自社での回収スキーム構築、消費者への啓発活動 |
失敗しないサステナブルなプラスチックの選び方

数ある選択肢の中から、自社に最適なサステナブルプラスチックを選ぶためには、多角的な視点での検討が不可欠です。
製品の用途と必要な性能を明確にする
まず最も重要なのは、「その製品にどのような機能が求められるか」を明確にすることです。
耐熱性、耐衝撃性、透明性、柔軟性、酸素バリア性など、製品の用途によって要求される性能は大きく異なります。
これらの要求性能を満たせる素材を候補として絞り込むことが第一歩となります。
素材のライフサイクル全体で評価する
原料調達から製造、使用、廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体(LCA:ライフサイクルアセスメント)で環境負荷を評価する視点が重要です。
「製造時のCO2排出量はどうか」「リサイクルは容易か」「生分解されるための条件は何か」など、一部分だけでなく、トータルで環境に貢献できる素材かを見極める必要があります。
認証マークの有無を確認する
信頼できる素材を選ぶための指標として、第三者機関による認証マークがあります。
例えば、バイオマスプラスチックの含有率を示す「バイオマスマーク」や、生分解性に関する基準を満たしたことを示す「生分解性プラマーク(グリーンプラ)」などがあります。
これらのマークは、素材の環境性能を客観的に証明する助けとなります。
供給の安定性とコストを総合的に判断する
どんなに優れた素材でも、安定的に調達できなければ製品化は困難です。原料の供給体制やメーカーの生産能力を確認し、事業継続性を担保できるかを見極めましょう。
その上で、製品の価格戦略と照らし合わせながら、最終的に導入する素材を決定することが、ビジネスとして成功させるための鍵となります。
| 選定ポイント | 確認事項 |
| 性能 | 製品に必要な耐熱性、耐衝撃性、透明性、柔軟性などを満たしているか? |
| ライフサイクル | 原料調達から廃棄まで、トータルでの環境負荷は低いか?リサイクルしやすいか? |
| 信頼性 | バイオマスマークや生分解性プラマークなどの第三者認証を取得しているか? |
| ビジネス性 | 安定的に供給されるか?製品コストに見合っているか? |
【業界別】サステナブルなプラスチックの活用事例

実際に、多くの企業がサステナブルなプラスチックの活用を進めています。具体的な事例を見ていきましょう。
食品容器・包装分野での活用事例
スターバックスコーヒーでは、2025年1月より、アイスビバレッジ用のストローを従来の石油由来プラスチック製から植物由来のバイオマス素材(カネカ社製「Green Planet®」生分解性バイオポリマー)に切り替えています。
このストローはバイオマス度99%を実現し、海水中や土壌中で自然に生分解される特性を持っています。
また、持ち帰り用の袋についても、バイオマス素材を配合したものに変更し、プラスチック使用量の削減に取り組んでいます。
日用品・雑貨分野での活用事例
アイグッズ株式会社は、抽出後のコーヒー粉とPLA樹脂を混合した素材「SUS coffee」を開発し、タンブラーやカトラリーセットなどのキッチン雑貨を製品化しています。
廃棄されるコーヒー粉をアップサイクルすると同時に、植物由来のPLAを使用することで、環境負荷のダブル削減を実現しています。
参考:コーヒーかすから生まれたおしゃれ食器が誕生!マグ&スプーン、プレートなど全4種 発売 | アイグッズ株式会社のプレスリリース
自動車・家電分野での活用事例
自動車業界では、内装部品などに植物由来のバイオプラスチックの採用が進んでいます。
例えば、マツダ株式会社は、内装意匠部品やシートの表皮材に、植物由来のバイオエンプラ(エンジニアリングプラスチック)を積極的に採用し、内外装での石油化学系プラスチックの使用率低減を目指しています。
参考:MAZDA NEWSROOMマツダ、無塗装で高質感のバイオエンジニアリングプラスチックを「マツダ ロードスター RF」の外装部品に採用|ニュースリリース
まとめ

本記事では、サステナブルなプラスチックの基礎知識から、具体的な種類、メリット・デメリット、そして企業が導入するための選定ポイントまでを解説しました。
プラスチックを取り巻く環境は大きく変化しており、環境配慮はもはやコストではなく、企業価値を高めるための重要な投資です。
この記事で得た知識を基に、ぜひ貴社の製品開発や事業戦略に最適なサステナブル素材の活用をご検討ください。
関連記事:シャンプーボトル素材の選び方は?種類別特徴とおすすめ活用法を紹介! – aims-online.com
\ 高品質なプラスチック容器が最小50本から買える! /

豊富なカラーバリエーションでおすすめの製品はこちら
業界トップクラスの商品数で製造から発送まで国内自社工場にて一括管理で安心。
-プラスチック容器のことならアイムスオンライン-
続きを読む: サステナブルなプラスチック素材の種類と特徴がわかる!企業の導入事例や選定ポイントも紹介