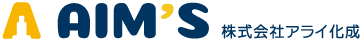目次
私たちの身の回りには、容器や家電、自動車部品など、数多くのプラスチック製品があふれています。しかし、屋外に置いたプランターが色褪せたり、長年使った洗濯バサミが突然砕けてしまったりした経験はないでしょうか。これらはすべて「プラスチックの劣化」が原因です。プラスチックは非常に便利な素材ですが、永遠にその性能を維持できるわけではありません。
この記事では、プラスチックがなぜ劣化するのか、その主な原因を分かりやすく解説します。また、製品の寿命をできるだけ延ばすための具体的な対策や、専門的な寿命の予測方法についてもご紹介します。製品を安全に、そして長く使い続けるための知識として、ぜひお役立てください。
プラスチックの劣化を引き起こす6つの主な原因
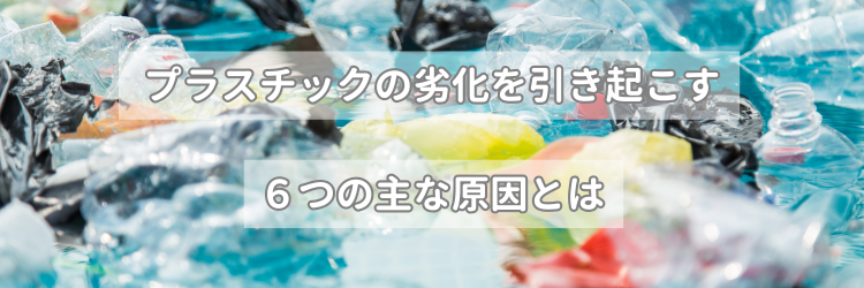
プラスチックの劣化は、単一の要因だけでなく、複数の要因が複雑に絡み合って進行します。ここでは、特に影響の大きい6つの原因について解説します。
光(紫外線)による劣化
太陽光に含まれる紫外線は、プラスチック劣化の最大の要因の一つです。プラスチックが紫外線のエネルギーを吸収すると、高分子の鎖が化学的に切断される「光酸化反応」が引き起こされます。これにより、変色や強度低下が進行します。特にポリカーボネート(PC)やポリプロピレン(PP)などは紫外線の影響を受けやすい素材です。
この現象は、屋外に置かれた車のヘッドライトカバーが黄ばんだり、公園の遊具の色が褪せたりする原因となっています。
熱による劣化
プラスチックは熱によっても劣化します。高温環境下に置かれると、プラスチック内の分子運動が活発になり、空気中の酸素と反応しやすくなります(熱酸化劣化)。これにより、分子構造が変化し、収縮や変形、もろくなる現象(脆化)を引き起こします。
全てのプラスチックには耐熱温度が定められており、これを超える環境での使用は劣化を著しく早める原因となります。
水(加水分解)による劣化
プラスチックの中には、水と反応して分解されてしまう性質を持つものがあります。この現象を「加水分解」と呼びます。ポリエチレンテレフタレート(PET)やポリカーボネート(PC)、ポリウレタン(PU)などが、エステル結合という水に弱い部分を持つため、加水分解しやすい代表的な樹脂です。
高温多湿の環境ではこの反応が促進されるため、日本の気候はプラスチックにとって過酷な環境と言えるかもしれません。
応力による劣化
応力とは、物体に外部から力が加わった際に、内部に生じる抵抗力のことです。製品の成形時に生じた目に見えないほどの小さな傷や気泡、設計上の鋭い角などに応力が集中すると、そこを起点に亀裂が発生し、劣化が進行します。
継続的に負荷がかかる部品や、締め付けが強すぎるネジ周りなどで、この種の劣化が見られます。
化学物質(有機溶剤・金属)による劣化
特定の化学物質との接触も劣化の要因です。有機溶剤はプラスチックを膨張させたり、溶かしたりする性質があります。また、一部の金属イオン(銅、マンガンなど)は、プラスチックの酸化反応を促進する触媒として働き、劣化を早めることがあります。
例えば、銅製の配線の被覆材としてポリプロピレン(PP)を使用する場合、銅イオンによる劣化を防ぐための特別な添加剤が必要になります。
材料自身の経時変化による劣化
外的要因が全くなくても、プラスチックは時間と共にゆっくりと変化していきます。成形後も内部で化学反応がわずかに進行したり、素材の柔軟性を保つために添加された「可塑剤」が徐々に気化して失われたりすることで、硬くなったり、もろくなったりします。これは、素材そのものが持つ宿命とも言える劣化要因です。
プラスチックの寿命を予測する方法とは?

製品の交換時期を判断したり、安全性を確保したりするために、プラスチックの寿命を予測することは非常に重要です。
しかし、様々な要因が絡むため、正確な予測は専門家でも難しいとされています。ここでは、一般的に用いられる寿命予測の考え方をご紹介します。
促進劣化試験の概要
製品が実際に使用される環境よりも厳しい条件(高温、高湿度、強い紫外線など)に意図的にさらし、劣化を人為的に加速させて、短時間で寿命を評価する試験を「促進劣化試験」と呼びます。
これにより、長期間にわたる使用でどのような変化が起こるかをシミュレーションします。
アレニウス法による寿命予測
促進劣化試験で得られたデータを用いて寿命を計算する代表的な手法が「アレニウス法」です。これは、「化学反応の速度は、温度が10℃上がると約2倍になる」という経験則(アレニウスの式)に基づいています。
複数の温度で劣化の進行度を測定し、その関係から、実際の使用温度環境下での寿命を推定します。この方法は、国際的な規格でも採用されている信頼性の高い評価方法の一つです。
プラスチックの劣化を防ぎ寿命を延ばすための対策

プラスチックの劣化を完全に止めることはできませんが、適切な対策を講じることで、その進行を大幅に遅らせ、製品の寿命を延ばすことが可能です。
保管環境を最適化する
劣化の主要因である光(紫外線)と熱、そして水分を避けることが最も基本的な対策です。
- 直射日光を避ける: 屋外で使用するものは、可能な限り日陰に置くか、使用しない時は屋内に保管しましょう。
- 高温多湿を避ける: 熱源の近くや、湿気の多い場所での保管は避けましょう。
- 適切な温度管理: 製品に表示されている耐熱・耐冷温度の範囲内で使用・保管することを徹底します。
紫外線対策を施す
屋外での使用が避けられない場合は、積極的な紫外線対策が有効です。
- UVカットコーティング: 自動車のヘッドライトや樹脂製のウッドデッキなどには、市販のUVカット機能付きコーティング剤を定期的に塗布することで、紫外線によるダメージを軽減できます。
- 色付きの製品を選ぶ: 一般的に、透明なプラスチックよりも顔料や添加剤が含まれた色付きのプラスチックの方が、紫外線を吸収・反射するため、耐候性が高い傾向にあります。
定期的な清掃とメンテナンス
製品の表面に付着した汚れや化学物質も劣化を促進します。酸性雨や鳥のフン、排気ガスなどが付着した場合は、速やかに水で洗い流し、中性洗剤で優しく洗浄することが大切です。
洗浄後は、水分をしっかりと拭き取ることも忘れないようにしましょう。
| 対策方法 | 具体的なアクション | 期待される効果 |
| 環境の最適化 | 直射日光、高温多湿を避けて保管する。 | 光、熱、水による劣化の進行を抑制する。 |
| 紫外線対策 | UVカットコーティング剤を塗布する。 | 紫外線による直接的なダメージを防ぎ、変色や強度低下を遅らせる。 |
| 清掃 | 表面の汚れを定期的に洗浄する。 | 酸性雨などの化学物質による腐食や、汚れの固着による劣化を防ぐ。 |
まとめ

本記事では、プラスチックが劣化する主な6つの原因と、その具体的な対策について解説しました。プラスチックの劣化は、光、熱、水、応力といった様々な要因が複雑に絡み合って進行します。
製品の特性を理解し、保管場所を工夫したり、定期的なメンテナンスを行ったりすることで、その寿命を大きく延ばすことが可能です。お使いのプラスチック製品をより長く、安全に活用するための一助となれば幸いです。
\ 高品質なプラスチック容器が最小50本から買える! /

\ おすすめの製品はこちら /
-プラスチック容器のことならアイムスオンライン-
続きを読む: プラスチックの劣化原因とは?寿命を延ばすための具体的な対策を解説